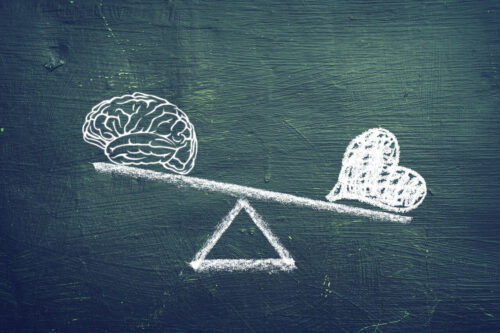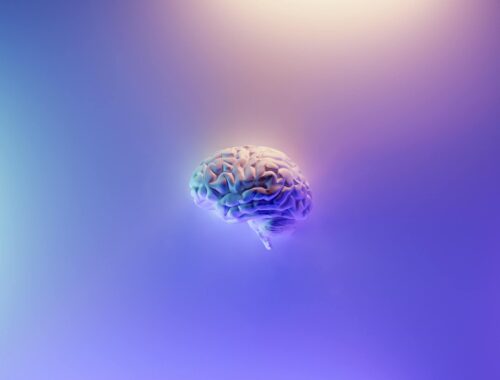YouTubeやVoicyにて、キングコング西野さんに取り上げられたことでも話題となった敵意帰属バイアス。
これは、認知バイアスという心理の一種であり、他者の言動を「敵意や悪意によるものだ」と思い込む傾向をさします。
この「敵意帰属バイアス」に陥ってしまったり、逆に陥らせてしまうことで、以下のような状況を引き起こすことがあります。
- 何気ない一言で、怒らせてしまった
- 相手の意見や説明を、嫌味に感じた
- 会話中、相手が不機嫌になってしまった
このように、日常では「無自覚・無意識」のうちに相手に敵意を与えてしまったり、自分が相手に敵意を感じてしまうことがありますよね。
そういった原因の大半は「敵意帰属バイアスによるもの」だと考えられますが、自分が陥ったり、相手に陥らせてしまうことで、人間関係を悪化さてしまったり、トラブルを引き起こしてしまう原因となってしまうこともあるでしょう。
そこで本記事では、敵意帰属バイアスの意味や原因・具体例などの詳細についてみていき、対処や改善をするには「どうすれば良いのか?」を紹介していきます。
キンコン西野さんが取り上げた敵意帰属バイアス(Ameba Blog)
敵意帰属バイアスとは

敵意帰属バイアスとは、他者の言動に対して「敵意・悪意があるものだ」と感じたり、そうであると思い込んでしまう心理現象で、自分や他者が意図して行ったか否か?は関係なく、受け取る側の一方的な解釈・捉え方(認知)に歪みが生じてしまうことで起こるものです。
例:会話や議論などで意見を言った人に対して「否定したいだけでしょ」と強く思い込んだり、嫉妬心などから「嫌味や悪口が言いたいだけに違いない」などと、相手の言動が攻撃(単なる否定)に感じてしまうこと、そう思い込むことに該当する。
敵意帰属バイアスは、認知心理学における認知バイアス(アンコンシャス・バイアス)の一種で、1986年にDodge(ダッジ)氏によって提唱された「社会的情報処理モデル(符号化・解釈)」が元となった心理現象。(以降、1994年にCrick&Dodgeによって改訂され、現在は6つの情報処理段階があるとされています。)
このように、他者の言動に対して「根拠のないこと」でも、悪意や敵意に感じる心理を「敵意帰属バイアス」といいます。
敵意帰属バイアスが起こる原因

- 本能
- 固定概念・思い込み
1. 本能(説)
敵意帰属バイアスの原因:1つ目は、人間の本能という説です。
これは、生物学的ジャンルになりますが『昔の人々は、知らない場所にいる集団を「敵意あるもの」として見ることにより、身の安全を確保してきた』と考えられています。
その名残が、現代では「あまり知らない人の言動を敵意によるものだ」と感じやすい傾向があると言われています。
ですから、敵意帰属バイアスのような認知(捉え方)に至ってしまい、あらゆるトラブルを引き起こしてしまうことがあると考えられています。
2. 固定概念・思い込み
敵意帰属バイアスの原因:2つ目は「育ち(環境・経験など)からくる固定概念や思い込みによるもの」だと考えられます。
これは「こうあるべき」や「常識」といったものに該当し、このような考え方によって敵意帰属バイアスが発動します。
例えば、道を歩くという行為だけでも「気配りのある(常識的な考えの)人」は、よく注意して歩いているでしょうし、それが当たり前で「皆そうするべきだ」と思い込んでいるでしょう。
しかし、そうでない考えの人も多く「ながらスマホ・不注意・横に並んで歩く」などの行為に及んでしまうことがあります。
これに対して「気配りある人」からすると、そんなことをするのは「わざとやってるに違いない」や「威張ってるに違いない」など、何らかの攻撃的な意図を感じてしまうことがあります。
そのため、敵意帰属バイアスが発動してトラブルの原因を作ってしまうわけです。このように、各々の「考え方(価値観)の違い」が常識や固定概念といった思い込みにあたり、両者がぶつかることによって敵意帰属バイアスは発動します。
敵意帰属バイアスの事例・具体例

- 悪口を言われてる様に見える。
- 意見が、悪口や否定、攻撃に感じる
- キンコン西野の質問への攻撃(実話)
1. 悪口を言いわれてる様に見える。
画像のような場面で、「自分の悪口を言ってるに違いない」と自然に思い込み、トラブルに発展する事例は少なくないでしょう。
確かに、このような言動をみて「勘違いを起こしてしまう気持ち」になるのもわかりますが、誰にも聞かれたくない話題、恥ずかしいと思う話題、別の誰かの話題などで盛り上がっているだけという可能性もあります。
そういった根拠や確証もないことに対して「自分のことだ」と思い込んでしまうことが、敵意帰属バイアスの働いている状態だといえるでしょう。
2. 意見が、悪口や否定、攻撃に感じる。
他者の意見やアドバイス、説明などにイラッとしたり、悪意や攻撃に感じてしまうことはあるでしょう。この時、何らかの思い込みからその様に感じて、敵意帰属バイアスが発動している可能性があります。
また思い込みといっても様々で、人によっても異なるでしょう。例えば、相手が自分に対して、嫌味、小馬鹿、嫉妬などを抱き「攻撃しているに違いない」という思い込みかもしれませんし「それに近しい何か」かもしれません。
このように、単なる意見やアドバイスに対して「敵意を向けられている」と感じるのも、敵意帰属バイアスが発動している一例にあたります。
3. キンコン西野の質問への攻撃(実話)
ここでは、キンコン西野さんの質問に対しての攻撃について、実際にあった事例をみていきましょう。
事の発端は、「西野亮廣講演会」のポスターデザイン。
オンラインサロン内では、「ああした方が良かったね」「こうした意図は何?」というように、日々、議論が飛び交っているそう。その流れで起きたのが、ポスターに採用された表紙でした。実際の質問がこちら
西野さん:集客のことだけを考えたら、写真の方がいいと思うんだけど、イラストにしたのは何か意図があるんですかね?
それへの回答者:〇〇(画家)さんが描いた絵を悪く言うのはやめて欲しい!!
という返答が返ってきたそうです。
またその後、サロンメンバーや西野さんが「意図を知りたかっただけだよ」と何度説明しても「悪く言うな・ひどい!」という趣旨の返答一点張りで、話が平行線となり進まなくなるという事態へ向かったそうです。
そこへ終止符を打ったのが「ビリギャル」の作者でお馴染みの坪田先生。
「そんなこと言ってないじゃん!」という内容を曲解して「責められた・攻撃された」と思いがちな人は、理解力や説明不足が原因ではなく、【敵意帰属バイアス】が原因だったりします。
そう一言放つと、颯爽に消えていったそうです(笑)
この話はここまでで「その後どうなったのか?」は、当時のサロンメンバーにしか知り得ないことです。
ともあれ、この質問が発端となり発動してしまった敵意帰属バイアス。
その紹介と、SNSでも似たような話は良くあるため「心においておくと良いですよね」というお話でした。
敵意帰属バイアスの対策・改善方法

認知バイアスは「常識がある種、偏った考え方」であるように、誰にでも起こりうる心理現象です。そのため、自分にも、相手にも、必ず陥る恐れがあります。
ですから「相手への対策方法」や「自分が陥ってしまった時の改善方法」について理解しておくことが大切です。
それでは、両者の方法についてみていきましょう。
敵意帰属バイアスに陥った相手への対策法
相手に「敵意帰属バイアス」が発動してしまったら、唯一の対策方法としてあげられるのは「それ以上、触れないこと」です。つまり、それ以上、相手に敵意を感じさせる行動を取らないことが、唯一の対策法となりえます。
なぜなら、敵意帰属バイアスが発動すると、どんなに説明をしても、どんなに誤解を解こうとしても、「相手は、その全てに対して攻撃と感じとってしまうから」です。
そのため、これ以上、攻撃の要因になる行動はせず、速やかに退却することが1番なのです。その後、落ち着いて話ができる機会に、言いたかったことを伝えるようにしましょう。
そうすることで、相手は話を聞いてくれる様になり、当時の誤解も解けるはずです。
敵意帰属バイアスに自分が陥った時の改善法
敵意帰属バイアスを改善していくには、「自分の中の常識」を疑ってみたり、「事実と感情」を分けて考える、物事を捉える、の2つが効果的でしょう。
なぜなら、「常識は偏った考え方」であり、「事実は正しいもので、感情は理想であることが多いから」です。
そのため「イラッとした時」や「敵意帰属バイアスの発動」を自分に感じた時は、「自分の中の当たり前や常識が、世間、もしくは目の前の人と一致しているか?」を考えてください。
また、事実であるか、感情であるかを考えることも試しましょう。もちろん、これは感情を大切にしないわけではありません。
事実を確かめる理由は、相手が「敵意や悪意で言っているのか?」を、見極めるためでもあります。もし事実が正しければ、相手にとっては「何かしらのアドバイスや変わって欲しいなどのメッセージ」という可能性が高いでしょう。
そのため、事実が正しいとわかれば、相手の攻撃性がないと感じることができるようになり、自然と感情も薄れていきます。
ゆえに、この2つを用いることで「敵意帰属バイアスの改善法」として、効果的に働きます。
まとめ
敵意帰属バイアスとは、他者の言動に対して「敵意・悪意がある」と思い込んでしまう心理現象。
そのため「相手への伝え方は注意すること」・「発動させてしまったら、そっとしておくこと」の2つを意識して、よい日常生活を送っていきましょう。
 のり
のりそれでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。
本記事が、読者さんと、活動のお役に立てると幸いです。
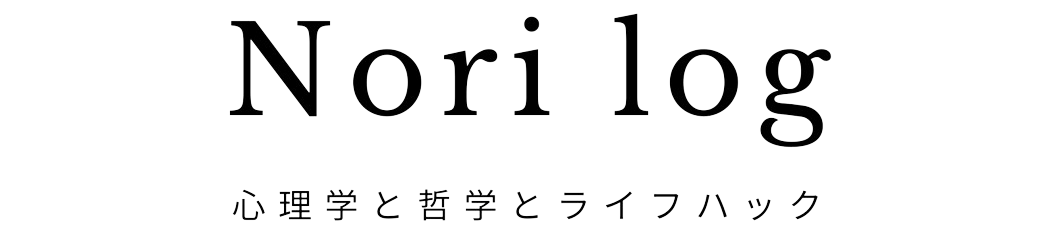



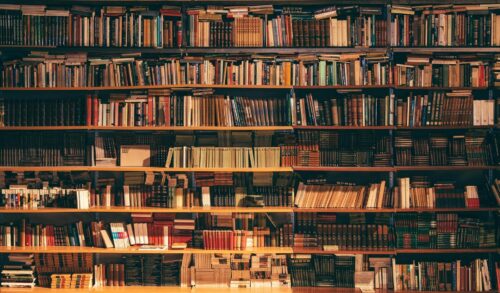
.jpg)