いきなりですが、あなたは『自分が「良いこと・悪いこと」について、どれほど理解できているだろうか?』と考えたことはあるだろうか。
私はしばし、考える機会があります。
とはいっても、現時点での結論は出ており、この記事の内容がまさしくそうです。
しかし、ときより「これは悪いことだ」という発言を目撃して「はたして、どうだろうか?」と改めて考えさせられる機会も少なくありません。
それは単に、善悪というものへの理解の差、もしくは違いがあるだけなのかもしれませんが、ここで紹介する「筆者の結論」を理解してくれることによって、皆さんの判断力に良い影響を与えることは明白です。
そこで、本記事では「そもそも良い・悪いとは何か?」その「判断基準とは何か?」について、自分なりの論理を展開していこうと思います。


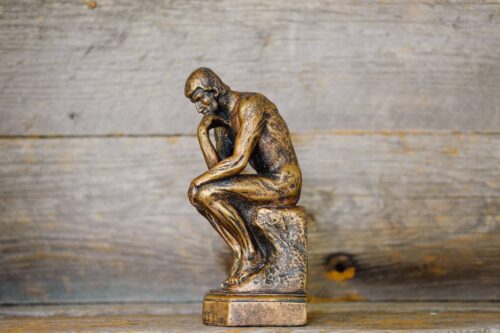
善悪とは何か?

善悪とは、多数の人間による都合で成り立っている。
そのため、多数の都合が良いと善、都合が悪いと悪、になります。
※当記事を読むにあたっての前提
ここでの内容は全て「善悪に正解・不正解的解はないこと、存在すらないこと」を前提に、善悪とな何か?について解説していることをご理解ください。
まずは結論から述べさせていただきましたが、下記では、その意味と判断基準について説明していきます。
善悪の意味とは?

上記の通り、善悪とは「多数の人間による都合の良し悪しで成り立つもの」と定義しましたが、一体なぜ、そのような結論に至ったのでしょうか。
答えはシンプルで、各々が「こうありたい」「こうするべきだ」といった思い込みや欲求、「嫌だ」「不愉快だ」といった防衛本能を持っているからです。
例えば、多くの人が「暴力はダメだ」イコール「それは悪だ」と述べるのは、そう発言する人にとって「不愉快・見ていて気持ちが悪い・自分がされると嫌・身内、知り合いがされると嫌」などといった、各々の都合の悪さが理由だからです。
これを先ほどの定義に基づいて噛み砕くと、暴力は私達(多くの人にとって)感情的都合が悪いから「嫌だ」「やめてほしい」といったもので、すなわち「悪だ」という発言に至るわけです。
このように、悪と呼ばれるものを突き詰めていくと、最終的に「各々の都合=その方向性が一致する=多数の都合」となるため、多数による都合の偏りこそが「善」か「悪」かの違いになると考えられます。
また、都合の良し悪しといっても様々で、人によっても異なります。例えば上記の「暴力はダメ」という例では、「不愉快・見ていて気持ちが悪い・自分がされると嫌・身内、知り合いがされると嫌」といった項目が存在していますが、人によって「複数もつ者」もいれば「1つだけもつ者」もいるでしょうし、上記には無いまた別の都合である場合も考えられます。
そのため、善悪は「多数による都合の良し悪しであり、一致する方向も同じである」ということになるわけです。
善悪は人によって異なるが、各々(多数)の都合で成り立つ。
また上記のことからわかるように、善悪(良い・悪い)に「正解・不正的解はなく、存在すら皆無である」といえます。なぜなら、全ては各々の都合に過ぎず、不快を避け、欲求を通したい言動に他ならないからです。
※コミュニティーや組織での「ルール・法律」を無視できるという意味ではありません。あくまで、善悪の意味を紐解いたものです。
以下では、日常に潜む言語化しづらい事象を、前述した理論に基づき解説してみました。
善悪の事例1:同僚の言い方
職場の同僚から「そのやり方じゃなくて、こうやってやった方がいいよ」と助言を受けることがありますよね。
このとき、当の本人からすれば単なるアドバイスであっても、受け手が「命令のように聞こえる」と感じれば、心理的リアクタンスが働き「自由を奪われた」と不快感を覚えて、受け手は「いや、このやり方でいい」と反発してしまうことがあります。
ここで「悪」とされる対象は立場によって変化します。
助言をする側からすれば「素直に従わない相手」が悪になりますし、助言を受けた側から見れば「自由を制限するような言い方をする相手」が悪となります。
しかし、周囲の多くの人にとっては「言い方がきつければ指摘した側の方が悪い」という感覚が共有されやすくなります。
そして、最終的に「悪」とされるのは“多数派の都合”に委ねられるわけです。
つまり「善悪」とは絶対的に存在するものではなく、各々の不快感や主観的な都合が集まり、それが一致した方向へ傾くことで成立しているのです。
善悪の事例2:友人のマウント
また、友人との会話でも同様のことが起こります。例えば「最近忙しいけど、俺は仕事のスキル上がってきてさ」という発言。
発言者は単に自分の近況を述べただけかもしれません。
しかし、聞き手によっては「自分を見下している」「自慢している」と受け取ってしまうことがあり、さらに「自分の現状(主観的都合)」があまり良くないと、強い不快感を抱くことがあります。
ここで「悪」とされたのは、発言そのものではなく、受け手の解釈や都合に過ぎません。
つまり「自分を下に見られた気がする」という主観的な不快感が「悪」というラベルを生むのです。
ただし、これを多数の人が目にした場合、「ただの報告を勝手にマウントと捉えるのは過剰だ」と評価する人もいれば、「言い方に配慮がないのはよくない」と発言者を悪とみなす人も出てきます。
最終的に、どちらが悪とされるかは「多数派の都合」によって決まるのであり、ここでも、絶対的な善悪が存在するわけではありません。
このように、善悪とは「各々の都合の方向性が一致すること」によって決まるもので、言ってしまえば多数決でしかないのです。
善悪の判断基準とは?

善悪の判断基準とは、道徳や常識、ルールや法律といったもので、現代の日本ではこれらに基づいて善悪の「区別・判断」を行なっている。
そのため、その時の状況や場所、環境や時代によっても善悪は異なってきます。
例えば、現代の表向きの日本では「道徳」という概念によって、おおよそ善悪の区別・判断ができるでしょう。
私たちは、学校や家庭で「道徳」という概念を学び育つため、日常会話や行動の中で「これは良いこと」「これはやってはいけないこと」という区別がスムーズに機能しますよね。
電車内で大声で通話する者がいれば「マナー違反だ」とされ、落とし物を拾って交番に届ければ「善い行いだ」と評価される。
こうした判断は、日本社会で共有されている「道徳心=常識」に基づいているわけです。
しかし、その他の国では違います。例えば、貧困が深刻な国や地域では、日本のように「道徳で解決できる状況」は存在しません。
人々は明日の食事を得るために必死であり、その場を生き延びることが最優先となります。
そこで発生する「盗み」や「賄賂」といった行為も、日本では明確に「悪」とされる一方で、そうした国では「生き抜くために必要な手段」と見なされることもあるのです。
つまり、善悪の判断は「その社会の都合」に強く依存しており、その社会の都合は時代によって変化します。
そのため、日本のような常識(判断基準)は、その他の国では通用しなくなり、あらゆる犯罪から日常的なコミュニケーションまで異なってくるわけです。
このように、善悪の判断基準は「取り締まるもの(国民の状況や常識・法律やルール)」が存在する上で成立するため、環境や時代によっても簡単に変わってしまうものなのです。
また、このように考えると善悪の基準は「国民の状況」「社会の常識」「法律やルール」といった“取り締まる枠組み”があって初めて成立していることがわかります。
それは裏を返せば、その枠組みが変われば、善悪の判断基準も簡単に書き換わってしまうということです。
これは歴史を振り返っても明らかです。かつて正義とされた行為が、今では犯罪とされることもあれば、その逆も存在します。
戦時中の英雄が、平和時には「暴力的な人物」と見なされ、奴隷制度が「当たり前」だった時代が、今では人権侵害として糾弾される。
これらはすべて、環境や時代の変化によって「取り締まるもの」が変化した結果です。
ゆえに、善悪の判断基準は特定のルール(道徳や法律など)でされるが、その基準は、状況や場所や時代といったあらゆる要因によって異なる。
これを書いた意図
ここでお伝えしたいことは「すべての善悪、そしてその判断基準は、これまで述べてきた通り“人間の都合”に依拠している」という考え方を提示したかったということです。
そして、これからの人生においては、この事実を理解した上で、自分自身の頭で考え、選択し、判断してほしい。
その思いでこの記事を書いています。
もちろん、これまで貴方が学んできた道徳観や常識、あるいは信じてきた価値観を否定するものではありません。
もし、この記事で示した内容とは異なる考え方を持っていたとしても、それもまた、立派な一つの見解であり、尊重されるべきものです。
大切にすべきものは「どちらが正しいか」「誰が間違っているか」といった二元論ではなく、物事の本質を探究し、その背後にあるロジックを理解した上で、自分なりの答えを導き出すことです。
だからこそ、この記事をきっかけに「善悪とは何か?」という問いを自分なりに考え直し、これからの人生に役立ててほしいと願っています。
また現代に生きる私たちは、こうした視点を持ちながら、道徳を育み、法律を整え、人間関係を築き、次の世代を教育していく必要があるのではないだろうか?
そのとき、表面的な「良い・悪い」ではなく、その意味や仕組みを本質的に理解していることが大前提となります。
ゆえに、「善悪とはそもそも何か?」を自分の言葉で説明できるくらいに理解しておくことは、今を生きる私たちにとって重要な課題のひとつだといえるでしょう。
まとめ
この記事は決して誰かを否定するために書いたものではありません。
「善悪の意味を理解したうえで人生を選び取っていく方が、きっと豊かで後悔の少ない生き方につながるのではないか」という考えをお伝えるもの。
つまり、ここで語った内容は一つの視点に過ぎないのです。
ですが、その視点を持つことで、あなた自身の選択や判断が、より深く、より自分らしいものになると、わたしは信じています。
これを機に、改めて自分自身に問いてみたり、考えてみる機会を作ってみてはいかがでしょうか。
 のり
のりそれでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。
本記事が、読者さんのお役に立てると幸いです。
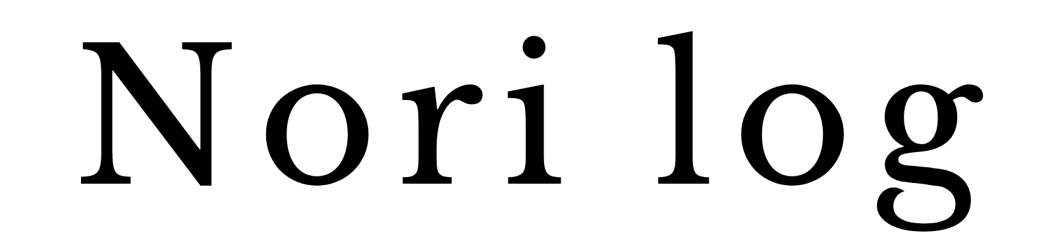

コメント